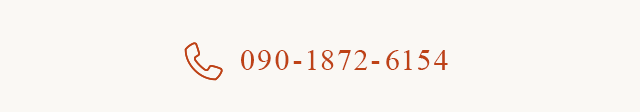皆さんこんにちは!
ゆくいどぅくまなんくるないさぁ、更新担当の中西です。
さて今回は
~“寄り道スポット”🏮~
街を歩いていると、夕暮れとともに赤ちょうちんが灯り始めますよね🏮
その灯りを見ると、なぜかホッとする…そんな経験はありませんか?
居酒屋は、
今回は、「居酒屋=ただの飲み屋さん」ではなく、
“まちの寄り道スポット”としての居酒屋の魅力を、
もう少し掘り下げてお話ししてみたいと思います😊
1. 暖簾をくぐる、その一歩目のドキドキをやわらげたい😳
初めてのお店に入るとき、ちょっと緊張しませんか?
-
「常連さんばかりだったらどうしよう…」
-
「一人客って浮かないかな…」
-
「何を頼んだらいいか分からない…」
そんな不安を少しでも減らしたくて、
私たちは“最初の30秒”をとても大事にしています⏱️
-
目が合ったらすぐに「いらっしゃいませ!」と笑顔でお出迎え😄
-
一人のお客様には、カウンターかテーブルか、好みを軽く確認
-
メニューの多さに迷っている様子なら、「よかったらおすすめお持ちしますね」と一声
最初の一言、最初の一皿がスムーズに届けば、
自然とそのお店の空気になじんでいただけます。
2. 常連さん文化と“初めてさん”のバランス⚖️
居酒屋には、多かれ少なかれ“常連さん文化”があります。
それ自体は、とてもありがたいことです。
-
仕事帰りに、ほぼ毎日のように顔を出してくださる方
-
「いつものね」の一言で好みが通じる方
-
新しいお客さんを連れてきてくださる方
常連さんは、お店にとって宝物です💎
でも、同時に大事なのは
「初めての方が入りづらい雰囲気にならないこと」。
そこで私たちは、
-
カウンターではスタッフも会話に入りつつ、“輪”が閉じないようにする
-
大声での“内輪ノリ”が続かないよう、さりげなく場を整える
-
初めてさんにも、さりげなく話しかけるきっかけをつくる
など、“居心地の中立性”を意識しています😊
「ここは常連さんも多いけど、初めてでも居やすいね」
そう言ってもらえることが、何より嬉しい褒め言葉です。
3. 一人飲み・少人数・大人数、それぞれの楽しみ方🎉
居酒屋は、「誰と何人で来るか」で表情が変わる場所でもあります。
◆ ① 一人飲みの世界🌙
一人飲みは、実はとても贅沢な時間。
-
好きなタイミングで入って
-
好きなペースで飲んで
-
好きなタイミングで帰る
誰にも合わせる必要がなく、
今日は軽く一杯だけ…という日もあれば、
しっぽり腰を据えて飲みたい日もあります。
一人飲みナビの例👇
-
最初の一杯+“すぐ出る一品”で落ち着く(例:なめろう、ポテサラ、冷やしトマト🍅)
-
店内を見渡して、今日はどんな雰囲気の日か感じる
-
余裕があれば、店員に「今日のおすすめ、軽めのものありますか?」と聞いてみる
-
締めは軽く一品(だし巻き玉子、お茶漬け、小さな丼ものなど)でほっとひと息
“自分の時間に戻れる場所”としての居酒屋も、なかなか良いものですよ😉
◆ ② 友人と二〜三人で🍻
少人数の飲みは、
「会話を楽しみたい」派にぴったり。
テーブル席でゆっくり語り合うもよし、
カウンターで“お店の人も含めた三人・四人”の時間を楽しむもよし。
距離感近めの会話を楽しみたいなら、
少人数での居酒屋利用が一番おすすめです😄
◆ ③ 宴会・打ち上げなど大人数で🎊
会社の歓迎会・送別会、仲間内の打ち上げ、同窓会など…。
大人数が集まるときも、居酒屋は大活躍です。
「騒がしくて他のお客様の迷惑にならないかな…」という不安も、
半個室や貸切対応ができれば解消されます。
事前に
「○時に乾杯したい」
「スピーチのタイミングで料理を一旦止めてほしい」
などご相談いただければ、
できる限り段取りのお手伝いもさせていただきますよ📣
4. メニューの“読み解き方”と、おすすめの頼み方📜
はじめてのお店でメニューを開くと、
びっしり並ぶ料理名に圧倒されてしまうこともありますよね😂
そんなときのコツを、こっそりお教えします。
◆ ① まずは「この店の顔」を探す👀
-
太字や枠で囲まれている
-
手書きポップがついている
-
「名物」「人気」と書かれている
こうしたメニューは、その店が自信を持っている一品であることが多いです。
まずはそこから一つ選んでみましょう✨
◆ ② バランスよく頼む“3ステップ”
-
冷たいもの(サラダ・刺身・冷菜など)🥗
-
温かいもの(焼き物・揚げ物・煮物など)🍢
-
締めの一品(ご飯物・麺類・デザート)🍚🍨
これを意識すると、
テーブルの上も、胃袋もバランスのよい流れになります。
◆ ③ 迷ったら「おまかせ」もアリ🙆♂️
人数・予算・好みを伝えて、
「このくらいのボリュームで、お酒に合う感じでおまかせできますか?」
と相談していただければ、
こちらでバランスを考えてコース風にお出しすることもできます。
5. 居酒屋が心がけている“ちょっとした気配り”✨
居酒屋側として、
お客様にはあまり見えないけれど大事にしていることがいくつかあります。
-
グラスが空きそうなタイミングで、“押しつけにならない”お声がけ
-
大事そうな話をしている席には、あえて長居しすぎないようにする
-
靴を脱ぐ座敷席では、足元の段差や荷物置きの場所にも気を配る
-
酔い具合を見ながら、強いお酒をすすめすぎない
居酒屋の仕事は、
単に料理を出してお酒を運ぶことではなく、
お客様それぞれの“今日のコンディション”に寄り添うことだと感じています🍀
6. これからの居酒屋が大事にしたいこと🌱
時代とともに、
働き方も、人と人の距離感も変わってきました。
そんな中で、居酒屋もまた少しずつ変化しています。
「お酒をたくさん飲める人だけが楽しむ場所」から、
**“いろんな人が、いろんなペースで楽しめる場所”**へ。
私たちは、そんな居酒屋でありたいと思っています😊
7. さいごに:あなたの毎日に、ちょっとした“寄り道”を🏮
まっすぐ家に帰る日もあれば、
ちょっとどこかに寄りたくなる日もありますよね。
-
今日は誰かと話したい日
-
今日は静かに飲みたい日
-
今日はちょっとお祝いしたい日
どんな日にも寄り添える場所として、
居酒屋はいつも暖簾を下げて、灯りをともしています🏮
「ただいま」と言うにはちょっと照れくさいけれど、
「おつかれ」と言い合える人たちがいる場所。
そんな**あなたの“もうひとつの居場所”**になれたら嬉しいです😊
今日も、明日も、明後日も。
それぞれの物語を抱えたお客様が、ふと立ち寄れるように——
私たちはカウンターを磨いて、
おいしいお酒と料理を用意して、お待ちしています🍺🍶✨